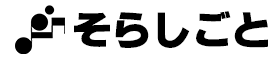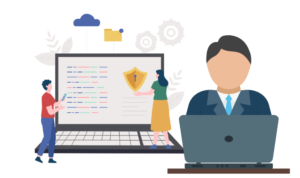ITゼネコンの終焉と新たな時代の幕開け
目次
ITゼネコンの終焉と新たな時代の幕開け

はじめに
システムエンジニアとして20年間、特にプログラミングの分野で活動してきた私にとって、IT業界の変遷を見続けています。いわゆる「ITゼネコン」の商流です。その時代の特徴は、大規模なITプロジェクトが多層のサプライチェーンで分割され、最下層に位置するエンジニアが大量のコーディング作業を担っていたことです。最近ではプログラミング案件が全体的に減ってきたと言われており、そして、今そのITゼネコン構造が終焉を迎えつつあり、新たなITの時代が到来しようとしています。
ITゼネコンとは何か?
まず、ITゼネコンとは何かについて整理しておきましょう。ITゼネコンとは、建設業界のゼネコン(ゼネラルコントラクター)になぞらえ、大手のIT企業が元請けとして大規模なシステム開発プロジェクトを受注し、それを多層のサブコントラクターに分割して発注する形態を指します。この構造では、プロジェクト全体を統括する大手企業が高い利益率を維持し、実際に手を動かして作業を行うエンジニアが従事する末端の企業は、低い利益率で大量の作業を行うことになります。
このモデルは、日本のIT業界の特徴的なスタイルであり、多くのシステムエンジニアが経験したことがあるでしょう。私もその一人です。商流の最下層に位置し、エンドユーザーからは遠く離れたところで、与えられた仕様に従ってひたすらコーディングを行う日々を送っていた時期もありました。
ITゼネコンの終焉
しかし、今このITゼネコンの構造が崩壊しつつあります。いくつかの要因がこれを後押ししています。
- アジャイル開発の普及
アジャイル開発が一般化するにつれ、従来のウォーターフォール型の開発モデルが持っていた多層の分業構造は時代遅れとなりました。アジャイルでは、チームが一体となって迅速にプロジェクトを進めることが求められるため、SESによる常駐やフリーランスはまだ活躍の場がありますが、ITゼネコンのような大規模で複雑な商流構造は逆効果となります。 - クラウドとSaaSの台頭
クラウドサービスやSaaS(Software as a Service)の普及により、システム構築の複雑さが大幅に減少しました。これにより、顧客自身が自らの手でシステムを構築・運用することが容易になり、ITゼネコンを介した大規模プロジェクトの必要性が低下しました。 - デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進
DXの流れは、企業が自社のITシステムを内製化する動きを加速させました。これにより、かつてはアウトソーシングされていたIT業務が社内に戻り、ITゼネコンの存在意義が薄れつつあります。
新たな時代の到来
ITゼネコンの終焉は、新たな時代の到来を告げています。従来の分業型開発から脱却し、エンジニアが直接顧客と対話しながら価値を提供する時代です。
- エンジニアの独立化
多くのエンジニアが独立し、フリーランスとして活動するようになっています。ITゼネコンの崩壊により、企業の内部や直接顧客と協働する機会が増え、エンジニアが自身の価値をより高めることが求められています。 - プロダクト志向の強化
システム開発は、単なるコーディング作業から、顧客の課題を解決するプロダクトを作ることに重きが置かれるようになっています。これにより、エンジニアには広範なスキルセットが要求され、商流の一部として機能するのではなく、プロダクトの価値を最大化する役割を担うことが求められます。 - 新しい商流の構築
これからのIT業界では、従来のゼネコン型商流に代わる、新しいビジネスモデルが登場するでしょう。たとえば、プロジェクトベースの柔軟なチーム編成や、顧客と直接契約するモデルが増加しています。エンジニアが自らのスキルを活かし、顧客と直接価値を共有することで、新たな商流が形成されるのです。
エンジニアが今取るべき行動
ITゼネコンの終焉は、エンジニアにとって大きな転換点です。これまでの経験に固執することなく、技術の進化に対応し、新たなビジネスモデルに柔軟に対応することが求められます。エンジニアのひとりひとりが、自らのスキルと経験を活かし、顧客に直接貢献する未来をITゼネコン終焉に向かう上で、選択肢として検討していく段階であると言われています。
これからのIT業界は、技術と人間の力が融合し、よりダイナミックに変化していくでしょう。ITゼネコンの終焉は、その変化の第一歩に過ぎません。未来を見据え、私たちエンジニアがどのようにその変化に適応し、新しい価値を創造していくかが、今問われているのです。
エンジニア視点での中小企業のIT人材内製化
社内の人員の一部を情報システム部に切り替えるもしくは兼任させる方法で内製化していく企業様を見ることがあります。最初のシステム導入や、その後の展開で専門家のエンジニアに頼るケースがあるかもしれませんが、勉強しながら何とか内製化しようとして進めています。ただ、これは上手くいく流れがあるように感じますが、一部の社員をIT人材に変化させていく上でモチベーションの問題が発生すると考えます。1つの企業のIT部分を担うというのは責任は重く、1つ間違えると業務停止のリスク等、社内でそのポジションを担うことを全うできるかがポイントです。
最初は軽いつもりで引き受けたが、いつの間にか情報システム部になっていたという覚悟がないままだと、担当業務が大きく変わることによるモチベーションの低下に繋がるリスクが伴います。いくらシステム導入がしやすくなったかといってもシステム間の連携等を管理していくのはかなり負担が大きいため、担当人材は転職したのと同じような意識が必要かもしれません。
エンジニアの中途採用
企業内部が整っていないにもかかわらず、いきなり中途採用したエンジニアを入れて上手くいかない可能性が高いという点です。中途採用で入社するエンジニアはITゼネコンのどのポジションにいたかという点がポイントです。大手のような上流であれば、下流の仕事は担っていないため難しく、また、下流の仕事を担っていた場合は上流の仕事が難しいということになります。要は中小企業で情報システム部のような位置づけを担うには上流から下流までの全ての仕事が出来ないといけないため、荷が重いということです。
弊社にはIT業務サポートというサービスがあります。中小企業に特化した仕事を幅広く行う業務委託で請け負うサービスです。ぜひご活用ください。